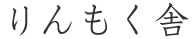奥さんと二人の息子が寝静まった夜に一人台所で豆の選別をします。ボールですくった豆を縁のある平たい板の上(そうめんの空箱上蓋)に空け、転がしながらクズ豆とゴミを選り分けて行きます。延々と繰り返される単調な作業。そのリズムが脳みその奥に仕舞われていた記憶を揺さぶり起こします。
20代後半、ぼくは愛媛の海沿いの村で蜜柑農家の手伝いをしていました。収穫期も終盤に差し掛かった12月の半ば、季節ハズレの大寒波で数日間山での仕事が休みになりました。
そんなある日、車で30分ほどの街まで買い物に出掛けました。行きしな、丘のような小さな山と山の間にかかる(笑えるくらい)クッキリとした虹を見ました。子供が絵に描いたような虹を見ました。
帰りしな、海の上にそそり立つ巨大な光の柱を見ました。護岸からほんの数十m先、手を伸ばせば届きそうな所に天に向かって伸びる真っ赤な光の柱を見ました。
仕事は翌日も休み。
夕方、山に張り付くようにあるその村の神社へでかけました。真っ黒い雲と粉雪が舞い。恐ろしいくらい真っ赤な夕陽が海に沈んでいきました。
その光景を眺め、ぼくは涙が止まりませんでした。
『もう戻れない場所まで来てしまったのだ』と、感じました。
ぼくがいま、農家をしている最初の一歩が、あの日の光柱と夕陽なのだといまはわかります。
『もう戻れない場所まで来てしまったのだ』その想いはいまも僕の胸の中に蹲っています。最後の時までを、何処で、何をして、どんな風に過ごすのか。
ぼくが農家になった理由がそこにあります。
無意識に脳みそが引っ張り出した記憶。
今日はそんな話でした。おしまい。