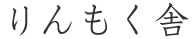淡路島来島の初日から師匠が用意してくれた仔猪を屠殺し解体までを体験することができた。久しぶりすぎて手際の悪さに不満が残る。たった三年間だったけれど京都に住んでいた頃に罠猟師をしていたから獣の命を懸けた猟が簡単なことではないと知っている。それでも恵まれるなら滞在中にもう一度経験したいとおもった。
夕方に師匠と一緒に近くの山の谷筋沿いへ罠を仕掛けに行く。谷底の小川の向こうが竹林で筍を食べにくる猪が多いと獣道の多さから推測ができる。数ある獣道のなかから地形を読みコレとおもう場所に14年ぶりに罠をかける。罠猟の免許は返上しているからあくまでも師匠の猟の手伝いで二箇所にかけた。
その晩から翌日にかけて雨が降り続く、ひとの痕跡と匂いを消してくれと捕獲の期待が高まる。翌日諸用を済ませて午後から師匠のかけた罠を見廻る。あちらこちらの山へ15ケ所ほど廻ったけれど空振り。当たり前だ!猟はそんなに甘くない。日が傾いた夕刻、先日かけた場所へ。半分諦め気味の師匠から“見といで”と言われひとりで谷へ降り竹林のなかへ。薄暗い竹林のなかで猪と目が合う。胸がドキっとする。“あー、この感覚はひさしぶりだ” 罠にかかった獣と出会う時は、いつも唐突だ。
師匠を呼びに戻る。“マジか!”と喜んでくれた。ふたりで現場へ戻り再度猪を間近で眺める。結構おおきい。80kgくらいだろうか?胸の鼓動がはやくなる。60mくらい離れた場所にかけたもうひとつの罠を一応確認に行く。斜面の上にいた猪と目が合う。“マジか!” まさかの二頭目。二日前にかけた二本の罠に二頭かかる。これは本当に有り得ない幸運で、師匠とふたりで“奇跡じゃん!”と興奮気味に讃え合う。
高揚した気を取り直してトメの準備にかかる。まずは最初にかかった大きな方を。久しぶりに対面するおとなの猪は、迫力満点。頭を下げて鼻でつちを跳ね上げ、キバをガチガチと噛み鳴らし威嚇してくる。逆立ったタテガミが身体をさらにおおきくみせる。高揚と興奮と恐怖が入り混じった感情が身体を包む。本当はじぶんでトメたかったけれど猪の大きさに怯み、師匠におねがいした。
輪っかにしたワイヤーを木の棒の先につけて怒り狂う猪の鼻先へ垂らす。ワイヤーに噛みついた瞬間に引き絞り連結したロープを渾身のちからを込めて木に縛りつける。罠のかかった前足と鼻面にかけたワイヤーで猪の動きに制限をかけて棍棒を眉間に打ち下ろすダンっと乾いた音がして猪は昏倒し横向きに倒れる。師匠が素早い動きで猪の元へ駆け寄り喉元からナイフを突き刺してトドメを刺す。一瞬の出来事。猪の目から命が消えてゆく。鮮やかすぎる。14年前に京都のやまで一緒に罠猟をしていた頃に比べて師匠の動きには一切の躊躇がない。経験を積んだ者の深さが垣間見えた。
放血を手早く済ませてから二頭目に取り掛かる。こちらは30kgくらいの子供。これならば、とじぶんで止め刺しをすることにした。前脚にかかったワイヤーに木の棒をかけて動きを制御してから後ろ脚を掴みひっくり返す。喉元からナイフを一気に突き立てる。胸骨裏の動脈を切る。手際が悪い。猪の意識が残っているのかブフッブフッと血の混じった泡を口角から流しながら断末魔の声を出す。不甲斐なさを感じながら猪の命が消えてゆくのを見守る。
腹を抜き、冷却のために小川に猪を浸ける。作業を終えた頃には、日はとっぷりと暮れて、深く暗い森がある。
山の神様と猪の命に感謝を捧げた。
命を奪うことに“かわいそう”って感情を持たなかった。そこには“ありがとう”しかなかった。
殺すことと生きることはおなじものの別のかたちで、奪うことでしかぼくらは生きてゆけない。かわいそうの感情を抱かなかった自分は、まだ大丈夫だとおもった。野菜を育てている時、野菜たちが“いま食べて”って語りかけてくる時が往々にしてある。命は循環する。食べることは途切れることではなく、受け継ぐことなんだとおもう。猪の命は、そんな当たり前のことを再確認させてくれた。ぼくはじぶんの手を汚し続けたい。生きることを感じ続けたい。
たった二本しかかけていない罠に、たったの3日の期間で、二頭の猪がかかる。猟をしたことがある人ならわかることだけれど、普通は有り得ない出来事。淡路島の森が、神様がぼくにプレゼントをしてくれたんじゃないか、とおもう。ぼくはまだ自然に愛されている、そんな気持ちになった。