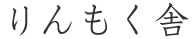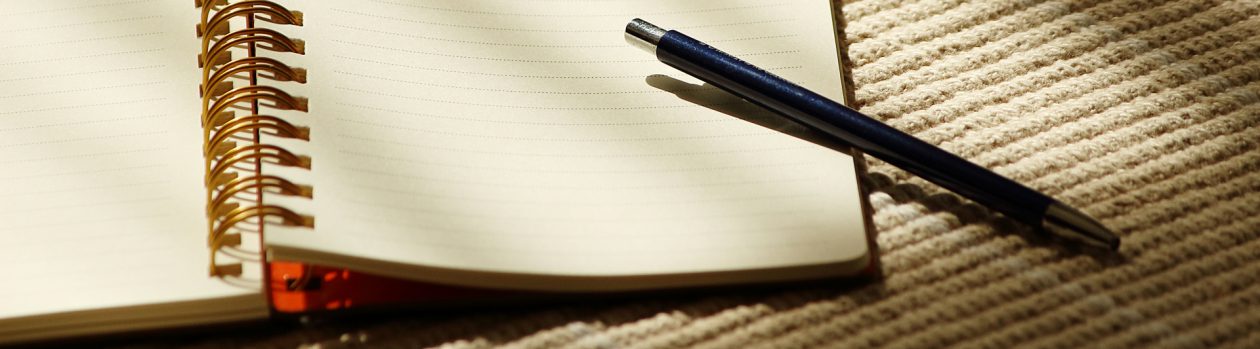日曜 長男が心待ちにしていた渓流(鳥居川)の解禁日、フリースクールの友人を誘って解禁八時の前に川に到着。まわりにはベテラン風のおじさん達がチラホラといます。迷惑にならないように少し外れた場所に陣取って釣り開始!小河川とは言え鳥居川は子供にとっては太く大きい。短い釣り竿ではポイントを探ることもできなくてまったく釣れない。仕方なくいつも行っている小川に移り、なんとかニジマスを一匹釣り上げました。
午後からは以前より予定していた雄鶏を〆ることにしました。夏に孵卵器で羽化させて大切に育てていた鶏です。友人夫婦とその娘ちゃん(次男とおなじ保育園)、それから急遽フリースクールの同校生も五人呼んで計らずも子供のための食育イベントになりました。
2羽いる雄鶏を代表の子供に驚かせないようにそっと捕まえさせます。抱きかかえられてキョトンとしている鶏を子供たちが撫でます。温かな体温が掌に伝わったことでしょう。木に吊るして相変わらずキョトンとしている雄鶏の首をナイフで切る。まったく抵抗する素振りはありません。バッと血が雪の上に滴り落ちます。泣き出した子もいたけれど殆どの子は、その様子を食い入る様に眺めていました。毛を毟る段になり「気持ち悪い」と逃げ出した子も数人いたけれど大丈夫な子達には丁寧に丸裸にしなさい、とお手伝いをさせました。身体の作りと内臓器官をひとつずつ説明しながら一番年長の子(養鶏と狩猟に興味津々)とぼくで鶏をバラしていきます。真剣な顔でさっきまで生きていた命に向き合う彼の姿にグッときました。いいね。
ちいさく切り分けた肉と内臓をめいめいが串に刺して炭火で焼き鳥。気がつくと気持ち悪いと言って逃げ出していた子達も戻ってきて苦心しながら仕込みに没頭しています。ジュウジュウとおいしそうな香り、焼きたての串焼きを我先にと口に運ぶ。「おいしいおいしい」の歓声が響きます。泣いていた子もおいしいとちゃんと食べている。四つしかない手羽をみんなで分けながら骨についた端肉も丁寧に食べる。最後に残った骨は愛犬のマメちゃんのお腹のなかへ。2羽分の肉が8人の子供達のおなかに収まりました。普段肉をあまり食べない子も「この肉なら食べられる!」と
雄鶏は、きっとしあわせでしたね。
生を奪うことに対して、かわいそう、怖い、気持ち悪いの感情を抱くことは別に悪くない。ある意味正常な反応です。それで肉を食べられなくなる事も別に悪いことだとは僕は思わない。想像を失い、誰か別の他人に殺させた肉を食べているコトに気が付かないフリをしている大人よりは余程マシだと思う。
ぼくらは他の命を奪うことでしかじぶんの命を繋ぐことができない。菜食主義者だって、野菜や果物の命を食べて生きている。野菜や果物を育てるために他の命は犠牲になっている。
鶏だってきっと かわいそうよりもおいしそう、っておもわれた方がしあわせだ。それが人のエゴだったとしてもかわいそうを引き継ぐよりもおいしそうを引き継いで生きていきたい。まぁ、こどもはそんな七面倒臭い考えなんて必要ないけどね。見て触り味わって、きっと全部が彼らのなかに残るはず。鶏さんありがとうございました。
ps.夕御飯時に長男が「魚を殺すときにはあんまりかわいそうとおもわないけれど、鶏はちょっとかわいそうっておもっちゃった」と小声で教えてくれました。息子よ、それでいいんだよ。